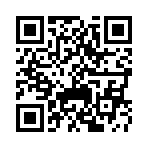2010年06月06日
早朝よりの予約が…

今日は屋島山上ホテルに泊まっている観光客からの
ボラガイド予約が入っている
8時半〜と、かなり早朝だ
頭の中のテープレコーダーは目が覚めるかな? (^_^;)
Posted by まだ親父 at 07:49│Comments(2)
│ボランティアガイド
この記事へのコメント
地球の裏側から考える
一. この曇天の下
理不尽な要求で先生にくってかかるエゴ丸出しの親、その親の挙動を映すかのようにはびこる学内のいじめ、医者に暴力を振るうモンスターペイシェント、政敵の足を引っ張っていれば 〝民意〞とやらを得て勝てる選挙、記事をねつ造 また言葉狩りよろしく相手をおとしめて正義ぶるマスコミ・・。
社会の一隅にひっそりと生きようとしている雄一郎ではあるが、すさびきったこの曇天の社会のもと、どうしてもその影に追われる日々となる。毎日、やり切れない思いで出口を求めている。
とかくこの世は住みにくい・・、某テレビではないが 〝渡る世間は鬼ばかり〞という様相を呈している。
それでもこの社会捨てたものでないというべきか、物ごとの本質を冷静に見極め、本音で現状の打開を提言しようとする人もなかにはいる。彼が喝采を送りたいのはそのような人で、貴重な存在だ。しかし現今、マスコミを筆頭に、そういう人の言葉尻を捕らえて、「スケープゴート」よろしくやり玉にする陰湿な風潮が蔓延している。
わが国を覆っているこの異様な雰囲気、おや、おや?と思う言論界の資質、彼が、何とかならぬかとため息をつくのはこのことだ。
ところで、早稲田大学の榊原教授が近年の著書で、「日本社会の幼児化」を挙げている。
榊原氏の云う幼児化とは、日々の生活の中で起こるいろいろな事象に対して、表層的な見方で安易に黒か白かで割り切り、それで納得している今の我々のマインドを指すと思われる。
言い換えれば、普段とちょっと変わったことが起こると、普段からの心構えがないものだからただただ面食らう。そして、その対処として、一見正論と思われる安易な答えを出して満足しようとする。このことで、自分たちの思考の欠如からくる不安をカバーしようとする。そういう状態ではなかろうか。
その何たるかを洞察するに必要な知識を持たずに、一般受けしそうな理屈にかこつけて一件落着、分かった気になっているのである。
要するに、最近はやりの言葉 〝民意〞とやらのレベルが、やたらと低い。幼稚なのだ。
現状に照らして、雄一郎も氏の解釈に大いにうなずくところがある。
バラエティ番組などで口先だけは達者になったにわか評論家。彼らが、変な自負心でまことしやかに言うコメントが、知識人、オピニオンリーダーの言として今の大衆に受ける。事実上世論を動かす力となっているのである。
かつて、一世を風靡した故大矢壮一氏の、テレビ時代を風刺した名言 〝一億総白痴化〞の言葉が、今またよみがえる。
他人、目上の人の意見に聞く耳を持たないばかりか、自分の権利を主張することばかり教えられてきた世代が、今まさにこの社会に君臨する時代になった。
だから今言った程度の〝民意〞レベルで、当然と言えばそうなのであるが、かねてから彼が心配していた戦後教育の弊害が、今を盛りとばかりに悪の花を咲かせているわけだ。このことに思いが及ぶと雄一郎は慄然と身震いする。
やれやれ、またまた、パロディー好きの彼のつぶやきが始まった・・。
ついでに、公序良俗についていえば、これがもう全然ダメ。かつては、欧米からも驚きをもって賞賛された日本人の礼儀正しさ、公共道徳であったが、今や目を覆うばかりに地に落ちてしまった。
前に、戦後日本の教育をダメにした元凶の一つに日教組がある・・と言った。だからこれは繰り返さないとしても、その教育で大きくなった親がしつけをできずに育ったその子供たち、また〝ゆとり教育〞とやらで絶対的なリテラシー不足の子供たち、その鬼っ子たちが今大人となって、モンスターとなって、この社会を各層から蝕(むしば)み始めているのだ。不都合な真実、えらいことだ。
同名の作品の著者ゴアさん、ゴメンナサイ・・。
自分達が躾(しつ)けられずに育ったものだから、自分達の子供をしつけるすべを知らない。
本来子供の躾けは、家庭で親がすべきものである。それにもかかわらず自分達の責任を棚にあげて、学校がしつけをしてくれるべきだと主張する。まことに本末転倒もいいところだが、病んだ社会にそれを諌(いさ)める浄化作用がない。
行く末はどうなることだろう・・、と彼がかねてから心配していたとおりとなってしまった。いやはや・・。
二. アンデスの儀式
南米はペルー。旋回するセスナの右窓、吐き気に悩まされながらパイロットの説明に眼下をのぞく。と、見えてきたのはナスカ地上絵の一つ、お猿さんだ。蚊取り線香のように見事に渦巻いた尻尾パターンからすると、古代人の意図したのは尾長ザルであろう。
今を去る4000年前、これら奇想天外なことを成したアンデスの民。彼らを突き動かした行動心理は、どのようなものだったのだろう。
雄一郎も会社を退職してすでに7年。夫婦ともに足腰が立つ今のうちに・・と、〝こんぴらの舞台 ?〞から飛び降りるつもりで、飛行機を数回乗り継ぎ約30時間、地球の裏側のこの地までやって来た。
前日の行程は、天空約3000メーターにあるマチュピチュ遺跡の探検 ?であった。
その深奥に踏み込んで見た地下牢と石の台は、彼の心を妙に騒がせ、この今も脳裏にこびりついている。というのも、それらは、それぞれ生贄(いけにえ)を閉じ込めまた解剖するところだったからである。
生贄といえば、心情穏やかならぬひびきがあるが、この地に限らず、エジプトを含め世界の遺跡でよくある話ではある。
古代人が自然の摂理の偉大さに感じた驚きとおののきは、ことのほかに大きかったことであろう。そこに神の存在を信じ捧げ物をすることになったのは、素朴とも当然ともいえる成り行きであったと思う。そして、最上の捧げものが「生贄」であると考えられたことは雄一郎にとっても想像に難くない。
生贄とは、その発想、それがおこなわれる社会の心理状態から、「身代わり」の意味合いのスケープゴートから、また「人身御供(じんしんごくう)」、「人柱」・・などの呼び名から容易にその起こりを類推できるものまで、多岐にわたっている。
わが国でも、人柱伝説が各地に残っているのは、知ってのとおりだ。
社会における行動心理学という点では、のちほど、この分野に造詣の深い浅野教授という人にご登場いただくとして、今しばらく雄一郎の悶々とした独り言に付き合うことにしよう。
彼が改めて認識したことに、生贄は,神への畏敬の念云々(うんぬん)ということとは別に、他人に責任や罪をなすりつける方便としても機能すること、またそれを主唱する媒介(メディア)が大きな役割を果たすことだ。
浅野教授の薫風?を受けた弟子、雄一郎。彼の意気がった分析によれば、さらにこのおどろおどろした生贄の機能は、病んだ今の社会の深層に巣くう「復讐」心理を満足させるための、また「見せしめ」のための手段に使われている。特に、ある種被害妄想に駆られた輩(やから)が牙を研ぐツールになっていると見る。
三. 現代版いけにえ
さらにである。彼がこと恐ろしく思うのは、この生贄の発想が、現に今の我が国の社会に強く生きのびていることである。決して古代の棺に封じ込められてしまったものではなかったのである。
そのひとつ・・。タブーの分野であろうが、誤解を恐れずあえてその例を示そう。
それは、2001年7月、兵庫県明石市で起こった花火見物客らの死傷事故の顛末(てんまつ)。
3~4000人の人がJR駅前歩道橋に殺到し、将棋倒しになった11名が死亡した事件である。
遺族の悲しみは大きく、それは容易に癒えるようなものではないであろう。
しかしここに、「おや、おや?」と思われる我が国の少しいびつな状況、場面が出てくるのである。
まずそれは、本件に関する一連の〝民意〞形成のされ方であった。メディアの取り上げ方も、扇情的で遺族を代弁する形をとった大衆に迎合する、それも執拗なものであった。
結局、やるかたなき現状のはけ口として、責任の所在が、事故の発生とは直接関係のない明石署の元副署長にあるとされてしまった。
その後の成り行きをはしょって言うと、裁判で、神戸地検は「元副署長が現場の状況を把握するのは困難で刑事責任を問うことはできない」として、何と4度にわたって不起訴処分を下した。
ところが、〝民意?〞はそんなものではないとばかり、9年後のこの今になって、新たに設けられた弁護士らを含む検察審査会が、直接の当事者でもない元副署長を起訴すべしと、地検とは逆の決議をするにいたったのである。
4度にわたる吟味を重ねた意思決定のプロセスは、何だったのだろうか。
似た例をもうひとつ・・。
それは、2005年4月、兵庫県尼崎市で起こったJR福知山線脱線事故。
乗務員の過失で高速の列車がカーブを曲がり切れず、乗客106人が犠牲になった事件である。
その後の裁判で、JR西幹部8人と歴代経営トップ3人について、現場の状況を直接に把握して指揮する立場になかったとして、また、事故電車の運転士については死亡を理由に、それぞれ不起訴処分とされた。
ところがどうであろう。前の花火見物事故の顛末同様、この件も5年後のこの今になって、直接の当事者でもない歴代社長3人を、起訴されるべき、としてしまったのである。
にわか心理学者気取りの雄一郎が分析するに、一連の経緯は、いずれも 〝草食化〞した、やわな男子だけのことでなく、癒しを求める今の病める社会と、それに迎合する新聞やテレビなどの 〝メディア〞の果たした役割が大きい。
ちょっと厳しい見方をすると
心情的に一般受けする、有ること・無いこと、まことしやかな解釈を大々的に伝搬し、恣意的な 〝民意〞を形成したこと。
そして、その必然の結果として、本件の処理として、持っていき場のない責任の所在を無理やり他に転嫁してしまったこと。
なるほど、よく見られる構図ではある。
しかし、まあ、本件の落着先は、天上の神様の思し召しとはまるで違ったものであろう。
・・と、雄一郎は想像する。
現状の説明として一見正論もどきに仕立て上げた理屈を声高らかにプロパガンダし、世論を誘導し仕切ることができるメディア。その実態は、現代における呪術師、巫女(みこ)であるとも言える。
特に新聞の場合、担当記者に記事を任せてしまう家内手工業的なやり方なので、その論調は、いきおい個人の信条、資質、思想に著しく左右されることになる。これが最高に危ない・・。
このようにして、この近年、わが国だけでしか通用しない〝常識?〞、諸外国とはちょっとずれたものの考え方、を国中に植えつけてしまった。高名なコメンテーターがいみじくも言った、いわゆる〝わが国の常識は、世界の非常識〞である。
ここに、〝幼児化〞の言葉が当てはまる。彼らの発言はある意味、正論にひびき共感を呼びやすい物事の一面をとらえて語られるので、聞く方としてはその場で反論しにくい厄介なものである。
結局は、すべての分野に、一見もっともらしいわが国独特の基準でしか物事の白黒を論じられない環境がつくられてしまった。
そうさせられた我々自身が気がつかないほどだから、彼ら呪術師の深謀遠慮さには、ある意味感服してしまうほどだ。
彼らは事実の歪曲、記事のねつ造を一向に反省もなく繰り返し、一部社会のがんとなって巣くっている。それが糾弾されずにいることが、雄一郎からすれば、この世の7不思議のひとつだ。
これらのことに考えが及ぶと、彼は、まさに近年のベストセラー本の題名ではないが、目の前に「バカの壁」がそびえ立っているかのような焦燥感を味わう。
新聞やマスコミなどが金科玉条、声高に主張する〝言論の自由〞とやらが、近年、一般の市民、遺族をひどく傷つけるケースが相次いでいる。松本サリン事件の善意通報者の受けた苦しみ、所沢市カイワレ大根業者の被った風評被害などなど、枚挙にいとまがない。
公器としてばかりではなく、ときに個人を世間からのバッシングにさらしたり自殺者を出す犠牲まで強いるなど、ある意味で恐ろしい凶器となって暴力を振るう。
実際の武器の場合は、これを製造するには厳しい規則、従事する人には資格が、それぞれ義務づけられているので、まだよい。だが、メディア業については、そういう歯止めとなるものがない。社会に広く重大な影響を与え、その力はとてつもなく大きいにもかかわらずだ。
当然、これを扱うにふさわしい倫理ある団体なのか、資格があるのか、が厳しくチェックされなければならない。彼が信じられないことに、それがないのだ。ただ有名無実な御用審査、社内審査委員会がある程度である。信じられない、絶句ものである。
ぜひ、国による厳格な審査制度を発足すべきだと雄一郎は思うが、どうであろう。
ここで一服。余談になるが、大相撲について。
横綱朝清龍を追い詰めたのも、雄一郎からすると、こうして形成されたわが国独特の狭量さによるものだ。
そらそら、彼の独り言がまた始まった。仕方ないなあ・・。
伝統・慣習が異なる異国の地にあって、一度はそのプレッシャーによって精神を病んだ28歳の若者。それを乗り越えて取り組んだ勝負に思わず出たガッツポーズにまで、国技・横綱にあるまじき行為と噛みついたハイエナ然たるメディア、えせ評論家、それに踊らされた相撲協会・・。
強過ぎてすっかり憎まれ役となった外人横綱であったが、オピニオン層の朝青龍への対応には、それだけでは済まさないバッシングがあった。
勝負の世界、相手を蹴落とす彼ぐらいの気迫がほしい。肉を食べるのに、最後まで箸を使えと強要するようなものだ。せっかく相撲に興味を持ち始めていた雄一郎であるが、おかげで今場所も全然面白くなくなってしまった。
なぜ周りは、もっと寛容でもって、人・物ごとを生かす度量ある態度がとれないのか。このことは、もちろん相撲に限ったことではない。
かつては、日本が好きでわが国に帰化することを考えていた朝青龍。わが国の相変わらずの島国根性が、一人の有能な青年を追いやってしまった。
その点同じ国技の柔道は、なんとか国際化に脱皮できたと思う。
青色の柔道着は日本の伝統にはそぐわないなどと、最初は欧米に反対して、いろいろ了見の狭いことを言っていたときもあった。が、その後日本柔道連盟はそれに固執することを避けた。そうでないと、現在のような国際的な地位はなかったことであろう。
四. 媒介者メディアとは
そもそも、メディアとは、ラテン語の「medius」からきており、その意は、神と人という異質なものを媒介する巫女などの霊媒を指す言葉である。
本来は中間の媒質であるべきものが、何を勘違いしたものか、偉そうに世間を睥睨し、指導的位置に立っていると錯覚してしまうので、恣意的な情報操作が容易にまかり通る
〝不都合な現実〞がある。
特に、朝日、毎日といった色めがねでものを見たがるメディアの存在、それは、それは、とても怖い。
余計な社説とか論説とかを気取る前に、起こった事象・情報を、都合のいい意図に加工したりせずありのままに伝えてほしい。判断は、われわれ読者が下したいのだから・・。
最近A新聞の勧誘員がしつこく来る。
「もっとましな記事を書け。 そしたらとってやる・・」、とまでの啖呵を切れない雄一郎であるが、それに近い嫌みを言ってしまった。
勧誘員にそんな事を云ったって、埒(らち)のあかない話なのに、やれやれ雄一郎も困ったものだ。
ここで、いよいよ浅野教授に登場してもらおう。教授は雄一郎の知る某心理学研究所の管理人でもある。
氏の研究によると、「集団妄想」という群集心理の概念が分析されている。
集団妄想(集団ヒステリー)とは、一定の集団に属する人たちが、自然の過酷な被害などの強いストレスにさらされるとあらぬ妄想に駆られるようになり、それを集団全体として確信することになることを言うらしい。
つまりは、ストレスからいっときも早く逃がれたいために、起こった現象が何であるかを「分かりやすい説明」に求め、それに納得、安心したくなる。ときにこれに対応して、都合のよい偏見や思い込みを具材とした理屈が、最も分かりやすい説明となるわけである。
だから、その出来上がった説明を声大きくプロパガンダできるカリスマ的存在、シャーマンならぬメディアが勢い主導し仕切るようになる。たちが悪いことに、このことがさらに集団妄想を強化するように働くということもある。
この結果、自分たちを絶対の正義と信じ込む盲信と、これに反対するものを徹底的に排撃するというシステムができあがってしまう。
この巧妙な仕掛けに気がついた者がいても、それを魔女狩りならぬ言葉狩りで徹底的に悪者に仕立てあげてしまう。
このシステムの一つの所産が、近世最大の集団妄想といわれる、ヨーロッパで起こった「魔女狩り」である。社会的弱者である女性が、ある意味ユダヤ人に代わる「スケープゴート」とされた経緯がある。
魔女の摘発には、うわさや密告がさかんに使われ、不安とストレスを増幅させるほか、妄想そのものを持続させる作用もした。
・・ざっとこれが、浅野教授によってなされた分析である。
雄一郎が生きるこの現代社会で、このメディアの悪さをさらに補強する役目をしている中間媒体が、限度を知らない、〝ああ言えばこう言う〞、策略を巡らすことに長けた弁護士族である。
もちろん、彼としても、弁護士を一把一からげにして烙印を押すつもりはない。
しかしこのところ、彼には、特権をかさにきたとしか思えない、弱者をいじめるいわゆる悪徳弁護士が増えてきているようにみえる。倫理を尊重すべき彼らが倫理をかなぐりすてて、あまりにも弁護のための弁護に明け暮れている。
裁判に際しても、被告側に、犯した罪を先ず否認することを吹き込むのが第一任務だと心得ているところがある。
そのせいか、最近の犯罪者は、国会議員であれ誰であれ、捕まっても自分の犯した罪状を認めない、先ず否認するという、卑怯さを人生訓としているかのような輩(やから)が増えた。
こう感じるのは雄一郎だけだろうか。 失礼。また話が飛んでしまった。
その資質を疑われるケースが相次ぐからであろう、教員免許と同様、国が弁護士資格の見直しをする意向だという。彼としては、むべなることかなと思う。民社党、日教組は、それに反対しているが・・。
五. その顛末は
さて、話は横にそれてしまったが、先に例に引いた2件の事故の顛末について考えてみよう。
肝心な点は、当該事故のような悲劇が再び起こらないようにすることだ。これは言うまでもないことで、皆さん異論はないであろう。
しかし、直接の当事者でもないものに責任を突き付けた、今回の検察審査会の〝生け贄措置〞。メディアの功が奏し?民意尊重とやらでできた審査会であるが、はたしてこの裁定で事故の再発は防げるのであろうか。いや、答えは明らかに否である。
ここらで国民が、ちょっと待てよと、理性に返り、真摯に考えてみる必要があるのではないか。
おそらく、例の花火事故に限らず、群集心理・パニックなどによる事故は、今回の措置とは無関係に再び起こることであろう。これは確かだ。
副署長に責任を無理に押し付けても、何の解決策にもなっていないからだ。
また、くだんの電車脱線事故についても同じことが言える。歴代社長何人に責任を取らせても、脱線するメカニズムは物理的に別にあるからである。ATS(列車自動停止装置)が必要だというなら、全国何百か所ものカーブがその対象となる。別の立場にいる社長が判断できるわけがない。
追及すべきは、高速の過密ダイヤで対処しなければならなくなった通勤地獄や社会システムそのものである。
とにかく、我々、一人一人がもう少し賢くならなければならない。
危機に際してのパニック、付和雷同。これに陥ることを避けるには、自分で考え自分で責任ある行動をとれるような、普段からの危機管理意識、教育訓練の徹底も必要であろう。誰かに付いて行ってそれで事故に遭ったら、その責任をその誰かに押し付ける。それでは駄目である。
もうひとつ。これが最も肝心な点である。
それは、今回のような措置の取られ方で、果たして、くだんの件の遺族が救われるかという問題だ。
端的に、原因を除去あるいは加害者を罰するという結果の裁判であれば、故人の御霊(みたま)も浮かばれるとする遺族もおられよう。
だが、今回のような責任の転嫁という決着で、はい、それで救われる、あきらめがつくという人がいたら、それこそ生贄の精神と同じではなかろうか。誰かに罪をかぶせて復讐を遂げるという話と変わらなくなってしまう。そんなことでは故人も喜ぶとは思えないし、遺族も後味の悪さを背負い続けなければならなくなる。決してこころに安穏が訪れる日は来ないであろう。
そうだ、人生に寄せる価値観は、十人十色(じゅうにんといろ)、心の持ちようも様々なのだ。
過去へのこだわりを生き甲斐とする意固地な老人にはなりたくない、過去を引きずらずに前向きに生きようと心のギアを入れ直した御遺族 。
いつまでも人間、過去にこだわってばかりいては生きていけない。これは天が定めた人間の生理に似て、賢く忘れ去ることもときに必要だと開き直っている方々 。
人の価値観はさまざまで、勝手な介在者にそれを押し付けられたくはない。
およそ、この世に生きて、この上なく幸せと感じている人がいたら、その人はどのような環境でどのような生き方をしているのだろうか。
雄一郎は、そのことに大いに興味がある。
因みに、人間が感じる〝幸せ感〞について、彼が心をひかれた事実がある。
それは、九州ほどの土地に約70万人がつましく暮らすヒマラヤの仏教国ブータン。
なんと、国民の97%が「とても幸せ」または「幸せ」と感じて生活しているという。このことは、2008年に実施された国勢調査で分かったそうである。
物質的な裕福さではわが国の足元にも及ばないブータンであるが、自然にあふれ、医療費や教育費がほぼ無料ということもあり、ほとんどの国民が満足と感じる、日本人が信じられない生活をしているのである。
ブータンからの留学生が、日本人は物質的な豊かさを手離さないことに懸命で、争いが多く、そんな日本のストレス社会を見ることが怖くなったともいう。
さて、
やっと心の平安を取り戻した人に対し、いたずらに過去を焚きつけようとする懲りないお節介屋さんがいるのである。人の心をもてあそぶ媒介屋さん、メディアは、罪が深いと言うほかはない。
ここでの話とは別であるが、
国同士の関係でも、中国や韓国の対日観に見る過去へのこだわり方は、異常さを通り越して救いようがないものとなっている。これで未来が志向できるのだろうか。
〝過去を風化させてはならない〞と、よくメディアが正義ぶって使うこの言葉は、建前上は立派な言葉であるが、実は普遍的に通用しないもので、場合によっては危険性を含んだスローガンとなる場合がある。いつもいさかいのもとを提供し続けるからだ。
ここに新しい哲学が要る。雄一郎はそう思う。
六. さて、どうするか
要点は、われわれ市井の人間がもう少し賢く生きなければならないということだ。
マスコミ、特に大衆紙で流される論調や情報を信じて疑わない人々がいることも、雄一郎にとっては信じられない驚異である。〝それ、ほんとよ。新聞が言っているから〞という調子だからだ。
子供の頃から新聞を教材の位置づけにおく感覚が養われたことで、書かれている内容を絶対正しいと信じ込む習慣ができている、言うなれば、すり込み現象があるのだ。
入試問題に朝日新聞の社説が取り上げられる、というようなことが何の疑問もなく習慣になっているのだから・・。
よほど我々の心に、〝新聞は公明正大だ〞という誤った迷信が根付いていることが分かる。
一人一人がしっかりした知見を持ち、自分自身で考える癖をつければ、現代の巫女、メディアに軽々に踊らされることもないであろうし、群集心理からくる付和雷同に陥る愚も犯さなくなるであろう。
悪徳弁護士にだまされること、また、甘いリップサービスに載せられて、優柔不断、海外に対しても恥さらしな首領をいただく政党を選ぶこともなくなるというものだ。
何が起こるか分からない混沌とした今の世、何でもありの時勢にあって、われわれ国民が論理的に冷静な判断でものごとに対処していけること、これがどれほど重要であるかは繰り返すまでもない。
市井の人々が自然の摂理・科学の知識をもう一寸だけ持ち合わせたならば、日々の
幾多の断面で我々は多くの恩恵を受け、また幸せな生活ができるだろうに・・と、雄一郎はよく思う。
神様が差し出してくれているこの上もない恵み・宇宙の真理、再生医療技術しかり、原子力エネルギーしかり。本来受けられるはずの恵みを、思慮がないばかりに享受できずにいるとしたら我々まことに不幸なことである。
無知からくる出口の見えない不毛な議論もいかに多いことか。
ひとつには、当事者が、科学的な論理的思考の欠如からくる片寄った先入観に惑わされているということが言える。
このところボケを気にし始めている雄一郎のようなものにとっても、この平成の世に漂っている科学マインドの欠如が非常に気がかりだ。
近年内閣府が行なった科学技術の関心の有無についての世論調査によれば、「関心がある」と答えたのは53%(前回98年:58%)と落ち、特に、18~29歳の若年層で41%にすぎないという結果が出ている。
また気になる一般市民の科学知識レベルはというと、海外経済開発機構(OECD)が実施した調査で、我が国は主要国中、何とビリから二番目(13位)なのだそうだ。
この現象の「犯人」の1つと目されるのが、1992年から小中学校に導入された「ゆとり教育」である。特に理科については合計1048時間あった授業時間が640時間に減り、最も理科の面白さを感じられる実験の時間が大幅に減っている。09年4月からはやや増やされているが、それでもわずか790時間である。
しかも、これから小中学校の教員になる世代はゆとり教育世代で、小中学校で実験を学んだ経験が少ない。さらに小学校の先生の約9割は、大学の出身学部が理科を学ぶ機会のない文系である。実験器具もゆとり教育の期間に処分されてしまっている。理科教育に復権のきざしがあるとはいっても、新たな教育を受けた先生が誕生するのは、何年も先のことなので気が遠くなる。
雄一郎も、ここまで科学教育が荒廃しているとは思っていなかったので暗然とする思いである。
戦後統治で我が国に降り立ったマッカーサは、「日本人は十二歳の少年と同じ」と云ったそうであるが、これは、日本人の現実を見る目がいかに甘く幼稚であるかということをいみじくも言い当てていると思う。
まだ多く残るこの精神構造から〝大人〞に脱皮するため、客観的なものの見方、論理的な思考が尊重される国となることを目指さなければならない。
なお、さらに彼がもってのほかと思うことに、学校の週休二日制がある。
「ゆとりある教育を」ということらしいが、子供に楽をさせて何が教育か、と云いたい。
結果は無残。 彼が予想していたとおり、かつて世界でも有数の学力水準の高い国であった日本は、今や見る影もなく地に落ちてしまった。
因みに、今の子供達〈中学生〉が思っている「将来の目標」を各国で調査した結果がある。
それによると、米国などでは、「社会のために貢献する」や「勉強がよくできる人間になる」が多いのに対して、日本では「その日その日を楽しく暮らす」が一番多い答えなのである。
何とまあ、志しの低いことであろうか。これでは雄一郎ならずとも、我が国の行方が心配になる人がいるのではないか。
今、草食化というか、日本人が内向きになっている傾向は、この10年で米大学への日本人留学生が4割減少したという事実にも表れている。
今年('10年3月)来日した米ハーバード大学のファウスト学長の指摘によれば、今年同大学が受け入れた留学生は、韓国人は200人、中国人は300人いるのに、日本人は何と一人だけということである。うそっ。何と、壊滅状態ではないか。
世界に打って出てチャレンジするという気概の喪失。この例だけからでも、危惧すべき状況がいかに如実になっているかが分かる。
七.我が心のルネッサンス
だが、嘆いてばかりいても仕方がない。今からでも遅くない。「世の中に今何が真に大
事なことか」、「してはいけないことは何なのか」といった初歩の初歩が、特に意識されるまでもなく国民誰もの血肉となっているような風土を取り戻したいものだ。
日本人がこれからの国際社会の荒波に伍していくためにも そうだ。 国民一人一人、物事の本質を見抜く怜悧な目を養いたいものだ。
世界は変わっている。このままでは日本は、骨太な論理、本質を追究する世界のグローバリーゼーションについて行けない。
繰り返すようだが、かつて世界から「教育水準の高い国民」といわれた風土をもう一度復興するのだ。
国の思い切った施策、教育体系の見直しがもちろん必要だ。
隗より始めよ。
叡知ある社会風土を育むため、先ずは、何としてでも学力離れに歯止めをかけるところか始めるのだ。
・・と、ここまで、人からは穏やかでおとなしいと見られている雄一郎にしては、めずらしく過激な心情を吐露してしまったようだ。
彼としては、なにも偉そうなことをいう性格の人間ではないのだが、いやむしろ反対の性向だが、ただ、毎日を人間らしく生きたいがためにもがいている。
彼が聞いたある人の言葉、
「何が人を人であるとしているかは、一にその人が、毎日を学び続ける、その努力をしている、かどうかということにある。」
を、今思い出している。
完
一. この曇天の下
理不尽な要求で先生にくってかかるエゴ丸出しの親、その親の挙動を映すかのようにはびこる学内のいじめ、医者に暴力を振るうモンスターペイシェント、政敵の足を引っ張っていれば 〝民意〞とやらを得て勝てる選挙、記事をねつ造 また言葉狩りよろしく相手をおとしめて正義ぶるマスコミ・・。
社会の一隅にひっそりと生きようとしている雄一郎ではあるが、すさびきったこの曇天の社会のもと、どうしてもその影に追われる日々となる。毎日、やり切れない思いで出口を求めている。
とかくこの世は住みにくい・・、某テレビではないが 〝渡る世間は鬼ばかり〞という様相を呈している。
それでもこの社会捨てたものでないというべきか、物ごとの本質を冷静に見極め、本音で現状の打開を提言しようとする人もなかにはいる。彼が喝采を送りたいのはそのような人で、貴重な存在だ。しかし現今、マスコミを筆頭に、そういう人の言葉尻を捕らえて、「スケープゴート」よろしくやり玉にする陰湿な風潮が蔓延している。
わが国を覆っているこの異様な雰囲気、おや、おや?と思う言論界の資質、彼が、何とかならぬかとため息をつくのはこのことだ。
ところで、早稲田大学の榊原教授が近年の著書で、「日本社会の幼児化」を挙げている。
榊原氏の云う幼児化とは、日々の生活の中で起こるいろいろな事象に対して、表層的な見方で安易に黒か白かで割り切り、それで納得している今の我々のマインドを指すと思われる。
言い換えれば、普段とちょっと変わったことが起こると、普段からの心構えがないものだからただただ面食らう。そして、その対処として、一見正論と思われる安易な答えを出して満足しようとする。このことで、自分たちの思考の欠如からくる不安をカバーしようとする。そういう状態ではなかろうか。
その何たるかを洞察するに必要な知識を持たずに、一般受けしそうな理屈にかこつけて一件落着、分かった気になっているのである。
要するに、最近はやりの言葉 〝民意〞とやらのレベルが、やたらと低い。幼稚なのだ。
現状に照らして、雄一郎も氏の解釈に大いにうなずくところがある。
バラエティ番組などで口先だけは達者になったにわか評論家。彼らが、変な自負心でまことしやかに言うコメントが、知識人、オピニオンリーダーの言として今の大衆に受ける。事実上世論を動かす力となっているのである。
かつて、一世を風靡した故大矢壮一氏の、テレビ時代を風刺した名言 〝一億総白痴化〞の言葉が、今またよみがえる。
他人、目上の人の意見に聞く耳を持たないばかりか、自分の権利を主張することばかり教えられてきた世代が、今まさにこの社会に君臨する時代になった。
だから今言った程度の〝民意〞レベルで、当然と言えばそうなのであるが、かねてから彼が心配していた戦後教育の弊害が、今を盛りとばかりに悪の花を咲かせているわけだ。このことに思いが及ぶと雄一郎は慄然と身震いする。
やれやれ、またまた、パロディー好きの彼のつぶやきが始まった・・。
ついでに、公序良俗についていえば、これがもう全然ダメ。かつては、欧米からも驚きをもって賞賛された日本人の礼儀正しさ、公共道徳であったが、今や目を覆うばかりに地に落ちてしまった。
前に、戦後日本の教育をダメにした元凶の一つに日教組がある・・と言った。だからこれは繰り返さないとしても、その教育で大きくなった親がしつけをできずに育ったその子供たち、また〝ゆとり教育〞とやらで絶対的なリテラシー不足の子供たち、その鬼っ子たちが今大人となって、モンスターとなって、この社会を各層から蝕(むしば)み始めているのだ。不都合な真実、えらいことだ。
同名の作品の著者ゴアさん、ゴメンナサイ・・。
自分達が躾(しつ)けられずに育ったものだから、自分達の子供をしつけるすべを知らない。
本来子供の躾けは、家庭で親がすべきものである。それにもかかわらず自分達の責任を棚にあげて、学校がしつけをしてくれるべきだと主張する。まことに本末転倒もいいところだが、病んだ社会にそれを諌(いさ)める浄化作用がない。
行く末はどうなることだろう・・、と彼がかねてから心配していたとおりとなってしまった。いやはや・・。
二. アンデスの儀式
南米はペルー。旋回するセスナの右窓、吐き気に悩まされながらパイロットの説明に眼下をのぞく。と、見えてきたのはナスカ地上絵の一つ、お猿さんだ。蚊取り線香のように見事に渦巻いた尻尾パターンからすると、古代人の意図したのは尾長ザルであろう。
今を去る4000年前、これら奇想天外なことを成したアンデスの民。彼らを突き動かした行動心理は、どのようなものだったのだろう。
雄一郎も会社を退職してすでに7年。夫婦ともに足腰が立つ今のうちに・・と、〝こんぴらの舞台 ?〞から飛び降りるつもりで、飛行機を数回乗り継ぎ約30時間、地球の裏側のこの地までやって来た。
前日の行程は、天空約3000メーターにあるマチュピチュ遺跡の探検 ?であった。
その深奥に踏み込んで見た地下牢と石の台は、彼の心を妙に騒がせ、この今も脳裏にこびりついている。というのも、それらは、それぞれ生贄(いけにえ)を閉じ込めまた解剖するところだったからである。
生贄といえば、心情穏やかならぬひびきがあるが、この地に限らず、エジプトを含め世界の遺跡でよくある話ではある。
古代人が自然の摂理の偉大さに感じた驚きとおののきは、ことのほかに大きかったことであろう。そこに神の存在を信じ捧げ物をすることになったのは、素朴とも当然ともいえる成り行きであったと思う。そして、最上の捧げものが「生贄」であると考えられたことは雄一郎にとっても想像に難くない。
生贄とは、その発想、それがおこなわれる社会の心理状態から、「身代わり」の意味合いのスケープゴートから、また「人身御供(じんしんごくう)」、「人柱」・・などの呼び名から容易にその起こりを類推できるものまで、多岐にわたっている。
わが国でも、人柱伝説が各地に残っているのは、知ってのとおりだ。
社会における行動心理学という点では、のちほど、この分野に造詣の深い浅野教授という人にご登場いただくとして、今しばらく雄一郎の悶々とした独り言に付き合うことにしよう。
彼が改めて認識したことに、生贄は,神への畏敬の念云々(うんぬん)ということとは別に、他人に責任や罪をなすりつける方便としても機能すること、またそれを主唱する媒介(メディア)が大きな役割を果たすことだ。
浅野教授の薫風?を受けた弟子、雄一郎。彼の意気がった分析によれば、さらにこのおどろおどろした生贄の機能は、病んだ今の社会の深層に巣くう「復讐」心理を満足させるための、また「見せしめ」のための手段に使われている。特に、ある種被害妄想に駆られた輩(やから)が牙を研ぐツールになっていると見る。
三. 現代版いけにえ
さらにである。彼がこと恐ろしく思うのは、この生贄の発想が、現に今の我が国の社会に強く生きのびていることである。決して古代の棺に封じ込められてしまったものではなかったのである。
そのひとつ・・。タブーの分野であろうが、誤解を恐れずあえてその例を示そう。
それは、2001年7月、兵庫県明石市で起こった花火見物客らの死傷事故の顛末(てんまつ)。
3~4000人の人がJR駅前歩道橋に殺到し、将棋倒しになった11名が死亡した事件である。
遺族の悲しみは大きく、それは容易に癒えるようなものではないであろう。
しかしここに、「おや、おや?」と思われる我が国の少しいびつな状況、場面が出てくるのである。
まずそれは、本件に関する一連の〝民意〞形成のされ方であった。メディアの取り上げ方も、扇情的で遺族を代弁する形をとった大衆に迎合する、それも執拗なものであった。
結局、やるかたなき現状のはけ口として、責任の所在が、事故の発生とは直接関係のない明石署の元副署長にあるとされてしまった。
その後の成り行きをはしょって言うと、裁判で、神戸地検は「元副署長が現場の状況を把握するのは困難で刑事責任を問うことはできない」として、何と4度にわたって不起訴処分を下した。
ところが、〝民意?〞はそんなものではないとばかり、9年後のこの今になって、新たに設けられた弁護士らを含む検察審査会が、直接の当事者でもない元副署長を起訴すべしと、地検とは逆の決議をするにいたったのである。
4度にわたる吟味を重ねた意思決定のプロセスは、何だったのだろうか。
似た例をもうひとつ・・。
それは、2005年4月、兵庫県尼崎市で起こったJR福知山線脱線事故。
乗務員の過失で高速の列車がカーブを曲がり切れず、乗客106人が犠牲になった事件である。
その後の裁判で、JR西幹部8人と歴代経営トップ3人について、現場の状況を直接に把握して指揮する立場になかったとして、また、事故電車の運転士については死亡を理由に、それぞれ不起訴処分とされた。
ところがどうであろう。前の花火見物事故の顛末同様、この件も5年後のこの今になって、直接の当事者でもない歴代社長3人を、起訴されるべき、としてしまったのである。
にわか心理学者気取りの雄一郎が分析するに、一連の経緯は、いずれも 〝草食化〞した、やわな男子だけのことでなく、癒しを求める今の病める社会と、それに迎合する新聞やテレビなどの 〝メディア〞の果たした役割が大きい。
ちょっと厳しい見方をすると
心情的に一般受けする、有ること・無いこと、まことしやかな解釈を大々的に伝搬し、恣意的な 〝民意〞を形成したこと。
そして、その必然の結果として、本件の処理として、持っていき場のない責任の所在を無理やり他に転嫁してしまったこと。
なるほど、よく見られる構図ではある。
しかし、まあ、本件の落着先は、天上の神様の思し召しとはまるで違ったものであろう。
・・と、雄一郎は想像する。
現状の説明として一見正論もどきに仕立て上げた理屈を声高らかにプロパガンダし、世論を誘導し仕切ることができるメディア。その実態は、現代における呪術師、巫女(みこ)であるとも言える。
特に新聞の場合、担当記者に記事を任せてしまう家内手工業的なやり方なので、その論調は、いきおい個人の信条、資質、思想に著しく左右されることになる。これが最高に危ない・・。
このようにして、この近年、わが国だけでしか通用しない〝常識?〞、諸外国とはちょっとずれたものの考え方、を国中に植えつけてしまった。高名なコメンテーターがいみじくも言った、いわゆる〝わが国の常識は、世界の非常識〞である。
ここに、〝幼児化〞の言葉が当てはまる。彼らの発言はある意味、正論にひびき共感を呼びやすい物事の一面をとらえて語られるので、聞く方としてはその場で反論しにくい厄介なものである。
結局は、すべての分野に、一見もっともらしいわが国独特の基準でしか物事の白黒を論じられない環境がつくられてしまった。
そうさせられた我々自身が気がつかないほどだから、彼ら呪術師の深謀遠慮さには、ある意味感服してしまうほどだ。
彼らは事実の歪曲、記事のねつ造を一向に反省もなく繰り返し、一部社会のがんとなって巣くっている。それが糾弾されずにいることが、雄一郎からすれば、この世の7不思議のひとつだ。
これらのことに考えが及ぶと、彼は、まさに近年のベストセラー本の題名ではないが、目の前に「バカの壁」がそびえ立っているかのような焦燥感を味わう。
新聞やマスコミなどが金科玉条、声高に主張する〝言論の自由〞とやらが、近年、一般の市民、遺族をひどく傷つけるケースが相次いでいる。松本サリン事件の善意通報者の受けた苦しみ、所沢市カイワレ大根業者の被った風評被害などなど、枚挙にいとまがない。
公器としてばかりではなく、ときに個人を世間からのバッシングにさらしたり自殺者を出す犠牲まで強いるなど、ある意味で恐ろしい凶器となって暴力を振るう。
実際の武器の場合は、これを製造するには厳しい規則、従事する人には資格が、それぞれ義務づけられているので、まだよい。だが、メディア業については、そういう歯止めとなるものがない。社会に広く重大な影響を与え、その力はとてつもなく大きいにもかかわらずだ。
当然、これを扱うにふさわしい倫理ある団体なのか、資格があるのか、が厳しくチェックされなければならない。彼が信じられないことに、それがないのだ。ただ有名無実な御用審査、社内審査委員会がある程度である。信じられない、絶句ものである。
ぜひ、国による厳格な審査制度を発足すべきだと雄一郎は思うが、どうであろう。
ここで一服。余談になるが、大相撲について。
横綱朝清龍を追い詰めたのも、雄一郎からすると、こうして形成されたわが国独特の狭量さによるものだ。
そらそら、彼の独り言がまた始まった。仕方ないなあ・・。
伝統・慣習が異なる異国の地にあって、一度はそのプレッシャーによって精神を病んだ28歳の若者。それを乗り越えて取り組んだ勝負に思わず出たガッツポーズにまで、国技・横綱にあるまじき行為と噛みついたハイエナ然たるメディア、えせ評論家、それに踊らされた相撲協会・・。
強過ぎてすっかり憎まれ役となった外人横綱であったが、オピニオン層の朝青龍への対応には、それだけでは済まさないバッシングがあった。
勝負の世界、相手を蹴落とす彼ぐらいの気迫がほしい。肉を食べるのに、最後まで箸を使えと強要するようなものだ。せっかく相撲に興味を持ち始めていた雄一郎であるが、おかげで今場所も全然面白くなくなってしまった。
なぜ周りは、もっと寛容でもって、人・物ごとを生かす度量ある態度がとれないのか。このことは、もちろん相撲に限ったことではない。
かつては、日本が好きでわが国に帰化することを考えていた朝青龍。わが国の相変わらずの島国根性が、一人の有能な青年を追いやってしまった。
その点同じ国技の柔道は、なんとか国際化に脱皮できたと思う。
青色の柔道着は日本の伝統にはそぐわないなどと、最初は欧米に反対して、いろいろ了見の狭いことを言っていたときもあった。が、その後日本柔道連盟はそれに固執することを避けた。そうでないと、現在のような国際的な地位はなかったことであろう。
四. 媒介者メディアとは
そもそも、メディアとは、ラテン語の「medius」からきており、その意は、神と人という異質なものを媒介する巫女などの霊媒を指す言葉である。
本来は中間の媒質であるべきものが、何を勘違いしたものか、偉そうに世間を睥睨し、指導的位置に立っていると錯覚してしまうので、恣意的な情報操作が容易にまかり通る
〝不都合な現実〞がある。
特に、朝日、毎日といった色めがねでものを見たがるメディアの存在、それは、それは、とても怖い。
余計な社説とか論説とかを気取る前に、起こった事象・情報を、都合のいい意図に加工したりせずありのままに伝えてほしい。判断は、われわれ読者が下したいのだから・・。
最近A新聞の勧誘員がしつこく来る。
「もっとましな記事を書け。 そしたらとってやる・・」、とまでの啖呵を切れない雄一郎であるが、それに近い嫌みを言ってしまった。
勧誘員にそんな事を云ったって、埒(らち)のあかない話なのに、やれやれ雄一郎も困ったものだ。
ここで、いよいよ浅野教授に登場してもらおう。教授は雄一郎の知る某心理学研究所の管理人でもある。
氏の研究によると、「集団妄想」という群集心理の概念が分析されている。
集団妄想(集団ヒステリー)とは、一定の集団に属する人たちが、自然の過酷な被害などの強いストレスにさらされるとあらぬ妄想に駆られるようになり、それを集団全体として確信することになることを言うらしい。
つまりは、ストレスからいっときも早く逃がれたいために、起こった現象が何であるかを「分かりやすい説明」に求め、それに納得、安心したくなる。ときにこれに対応して、都合のよい偏見や思い込みを具材とした理屈が、最も分かりやすい説明となるわけである。
だから、その出来上がった説明を声大きくプロパガンダできるカリスマ的存在、シャーマンならぬメディアが勢い主導し仕切るようになる。たちが悪いことに、このことがさらに集団妄想を強化するように働くということもある。
この結果、自分たちを絶対の正義と信じ込む盲信と、これに反対するものを徹底的に排撃するというシステムができあがってしまう。
この巧妙な仕掛けに気がついた者がいても、それを魔女狩りならぬ言葉狩りで徹底的に悪者に仕立てあげてしまう。
このシステムの一つの所産が、近世最大の集団妄想といわれる、ヨーロッパで起こった「魔女狩り」である。社会的弱者である女性が、ある意味ユダヤ人に代わる「スケープゴート」とされた経緯がある。
魔女の摘発には、うわさや密告がさかんに使われ、不安とストレスを増幅させるほか、妄想そのものを持続させる作用もした。
・・ざっとこれが、浅野教授によってなされた分析である。
雄一郎が生きるこの現代社会で、このメディアの悪さをさらに補強する役目をしている中間媒体が、限度を知らない、〝ああ言えばこう言う〞、策略を巡らすことに長けた弁護士族である。
もちろん、彼としても、弁護士を一把一からげにして烙印を押すつもりはない。
しかしこのところ、彼には、特権をかさにきたとしか思えない、弱者をいじめるいわゆる悪徳弁護士が増えてきているようにみえる。倫理を尊重すべき彼らが倫理をかなぐりすてて、あまりにも弁護のための弁護に明け暮れている。
裁判に際しても、被告側に、犯した罪を先ず否認することを吹き込むのが第一任務だと心得ているところがある。
そのせいか、最近の犯罪者は、国会議員であれ誰であれ、捕まっても自分の犯した罪状を認めない、先ず否認するという、卑怯さを人生訓としているかのような輩(やから)が増えた。
こう感じるのは雄一郎だけだろうか。 失礼。また話が飛んでしまった。
その資質を疑われるケースが相次ぐからであろう、教員免許と同様、国が弁護士資格の見直しをする意向だという。彼としては、むべなることかなと思う。民社党、日教組は、それに反対しているが・・。
五. その顛末は
さて、話は横にそれてしまったが、先に例に引いた2件の事故の顛末について考えてみよう。
肝心な点は、当該事故のような悲劇が再び起こらないようにすることだ。これは言うまでもないことで、皆さん異論はないであろう。
しかし、直接の当事者でもないものに責任を突き付けた、今回の検察審査会の〝生け贄措置〞。メディアの功が奏し?民意尊重とやらでできた審査会であるが、はたしてこの裁定で事故の再発は防げるのであろうか。いや、答えは明らかに否である。
ここらで国民が、ちょっと待てよと、理性に返り、真摯に考えてみる必要があるのではないか。
おそらく、例の花火事故に限らず、群集心理・パニックなどによる事故は、今回の措置とは無関係に再び起こることであろう。これは確かだ。
副署長に責任を無理に押し付けても、何の解決策にもなっていないからだ。
また、くだんの電車脱線事故についても同じことが言える。歴代社長何人に責任を取らせても、脱線するメカニズムは物理的に別にあるからである。ATS(列車自動停止装置)が必要だというなら、全国何百か所ものカーブがその対象となる。別の立場にいる社長が判断できるわけがない。
追及すべきは、高速の過密ダイヤで対処しなければならなくなった通勤地獄や社会システムそのものである。
とにかく、我々、一人一人がもう少し賢くならなければならない。
危機に際してのパニック、付和雷同。これに陥ることを避けるには、自分で考え自分で責任ある行動をとれるような、普段からの危機管理意識、教育訓練の徹底も必要であろう。誰かに付いて行ってそれで事故に遭ったら、その責任をその誰かに押し付ける。それでは駄目である。
もうひとつ。これが最も肝心な点である。
それは、今回のような措置の取られ方で、果たして、くだんの件の遺族が救われるかという問題だ。
端的に、原因を除去あるいは加害者を罰するという結果の裁判であれば、故人の御霊(みたま)も浮かばれるとする遺族もおられよう。
だが、今回のような責任の転嫁という決着で、はい、それで救われる、あきらめがつくという人がいたら、それこそ生贄の精神と同じではなかろうか。誰かに罪をかぶせて復讐を遂げるという話と変わらなくなってしまう。そんなことでは故人も喜ぶとは思えないし、遺族も後味の悪さを背負い続けなければならなくなる。決してこころに安穏が訪れる日は来ないであろう。
そうだ、人生に寄せる価値観は、十人十色(じゅうにんといろ)、心の持ちようも様々なのだ。
過去へのこだわりを生き甲斐とする意固地な老人にはなりたくない、過去を引きずらずに前向きに生きようと心のギアを入れ直した御遺族 。
いつまでも人間、過去にこだわってばかりいては生きていけない。これは天が定めた人間の生理に似て、賢く忘れ去ることもときに必要だと開き直っている方々 。
人の価値観はさまざまで、勝手な介在者にそれを押し付けられたくはない。
およそ、この世に生きて、この上なく幸せと感じている人がいたら、その人はどのような環境でどのような生き方をしているのだろうか。
雄一郎は、そのことに大いに興味がある。
因みに、人間が感じる〝幸せ感〞について、彼が心をひかれた事実がある。
それは、九州ほどの土地に約70万人がつましく暮らすヒマラヤの仏教国ブータン。
なんと、国民の97%が「とても幸せ」または「幸せ」と感じて生活しているという。このことは、2008年に実施された国勢調査で分かったそうである。
物質的な裕福さではわが国の足元にも及ばないブータンであるが、自然にあふれ、医療費や教育費がほぼ無料ということもあり、ほとんどの国民が満足と感じる、日本人が信じられない生活をしているのである。
ブータンからの留学生が、日本人は物質的な豊かさを手離さないことに懸命で、争いが多く、そんな日本のストレス社会を見ることが怖くなったともいう。
さて、
やっと心の平安を取り戻した人に対し、いたずらに過去を焚きつけようとする懲りないお節介屋さんがいるのである。人の心をもてあそぶ媒介屋さん、メディアは、罪が深いと言うほかはない。
ここでの話とは別であるが、
国同士の関係でも、中国や韓国の対日観に見る過去へのこだわり方は、異常さを通り越して救いようがないものとなっている。これで未来が志向できるのだろうか。
〝過去を風化させてはならない〞と、よくメディアが正義ぶって使うこの言葉は、建前上は立派な言葉であるが、実は普遍的に通用しないもので、場合によっては危険性を含んだスローガンとなる場合がある。いつもいさかいのもとを提供し続けるからだ。
ここに新しい哲学が要る。雄一郎はそう思う。
六. さて、どうするか
要点は、われわれ市井の人間がもう少し賢く生きなければならないということだ。
マスコミ、特に大衆紙で流される論調や情報を信じて疑わない人々がいることも、雄一郎にとっては信じられない驚異である。〝それ、ほんとよ。新聞が言っているから〞という調子だからだ。
子供の頃から新聞を教材の位置づけにおく感覚が養われたことで、書かれている内容を絶対正しいと信じ込む習慣ができている、言うなれば、すり込み現象があるのだ。
入試問題に朝日新聞の社説が取り上げられる、というようなことが何の疑問もなく習慣になっているのだから・・。
よほど我々の心に、〝新聞は公明正大だ〞という誤った迷信が根付いていることが分かる。
一人一人がしっかりした知見を持ち、自分自身で考える癖をつければ、現代の巫女、メディアに軽々に踊らされることもないであろうし、群集心理からくる付和雷同に陥る愚も犯さなくなるであろう。
悪徳弁護士にだまされること、また、甘いリップサービスに載せられて、優柔不断、海外に対しても恥さらしな首領をいただく政党を選ぶこともなくなるというものだ。
何が起こるか分からない混沌とした今の世、何でもありの時勢にあって、われわれ国民が論理的に冷静な判断でものごとに対処していけること、これがどれほど重要であるかは繰り返すまでもない。
市井の人々が自然の摂理・科学の知識をもう一寸だけ持ち合わせたならば、日々の
幾多の断面で我々は多くの恩恵を受け、また幸せな生活ができるだろうに・・と、雄一郎はよく思う。
神様が差し出してくれているこの上もない恵み・宇宙の真理、再生医療技術しかり、原子力エネルギーしかり。本来受けられるはずの恵みを、思慮がないばかりに享受できずにいるとしたら我々まことに不幸なことである。
無知からくる出口の見えない不毛な議論もいかに多いことか。
ひとつには、当事者が、科学的な論理的思考の欠如からくる片寄った先入観に惑わされているということが言える。
このところボケを気にし始めている雄一郎のようなものにとっても、この平成の世に漂っている科学マインドの欠如が非常に気がかりだ。
近年内閣府が行なった科学技術の関心の有無についての世論調査によれば、「関心がある」と答えたのは53%(前回98年:58%)と落ち、特に、18~29歳の若年層で41%にすぎないという結果が出ている。
また気になる一般市民の科学知識レベルはというと、海外経済開発機構(OECD)が実施した調査で、我が国は主要国中、何とビリから二番目(13位)なのだそうだ。
この現象の「犯人」の1つと目されるのが、1992年から小中学校に導入された「ゆとり教育」である。特に理科については合計1048時間あった授業時間が640時間に減り、最も理科の面白さを感じられる実験の時間が大幅に減っている。09年4月からはやや増やされているが、それでもわずか790時間である。
しかも、これから小中学校の教員になる世代はゆとり教育世代で、小中学校で実験を学んだ経験が少ない。さらに小学校の先生の約9割は、大学の出身学部が理科を学ぶ機会のない文系である。実験器具もゆとり教育の期間に処分されてしまっている。理科教育に復権のきざしがあるとはいっても、新たな教育を受けた先生が誕生するのは、何年も先のことなので気が遠くなる。
雄一郎も、ここまで科学教育が荒廃しているとは思っていなかったので暗然とする思いである。
戦後統治で我が国に降り立ったマッカーサは、「日本人は十二歳の少年と同じ」と云ったそうであるが、これは、日本人の現実を見る目がいかに甘く幼稚であるかということをいみじくも言い当てていると思う。
まだ多く残るこの精神構造から〝大人〞に脱皮するため、客観的なものの見方、論理的な思考が尊重される国となることを目指さなければならない。
なお、さらに彼がもってのほかと思うことに、学校の週休二日制がある。
「ゆとりある教育を」ということらしいが、子供に楽をさせて何が教育か、と云いたい。
結果は無残。 彼が予想していたとおり、かつて世界でも有数の学力水準の高い国であった日本は、今や見る影もなく地に落ちてしまった。
因みに、今の子供達〈中学生〉が思っている「将来の目標」を各国で調査した結果がある。
それによると、米国などでは、「社会のために貢献する」や「勉強がよくできる人間になる」が多いのに対して、日本では「その日その日を楽しく暮らす」が一番多い答えなのである。
何とまあ、志しの低いことであろうか。これでは雄一郎ならずとも、我が国の行方が心配になる人がいるのではないか。
今、草食化というか、日本人が内向きになっている傾向は、この10年で米大学への日本人留学生が4割減少したという事実にも表れている。
今年('10年3月)来日した米ハーバード大学のファウスト学長の指摘によれば、今年同大学が受け入れた留学生は、韓国人は200人、中国人は300人いるのに、日本人は何と一人だけということである。うそっ。何と、壊滅状態ではないか。
世界に打って出てチャレンジするという気概の喪失。この例だけからでも、危惧すべき状況がいかに如実になっているかが分かる。
七.我が心のルネッサンス
だが、嘆いてばかりいても仕方がない。今からでも遅くない。「世の中に今何が真に大
事なことか」、「してはいけないことは何なのか」といった初歩の初歩が、特に意識されるまでもなく国民誰もの血肉となっているような風土を取り戻したいものだ。
日本人がこれからの国際社会の荒波に伍していくためにも そうだ。 国民一人一人、物事の本質を見抜く怜悧な目を養いたいものだ。
世界は変わっている。このままでは日本は、骨太な論理、本質を追究する世界のグローバリーゼーションについて行けない。
繰り返すようだが、かつて世界から「教育水準の高い国民」といわれた風土をもう一度復興するのだ。
国の思い切った施策、教育体系の見直しがもちろん必要だ。
隗より始めよ。
叡知ある社会風土を育むため、先ずは、何としてでも学力離れに歯止めをかけるところか始めるのだ。
・・と、ここまで、人からは穏やかでおとなしいと見られている雄一郎にしては、めずらしく過激な心情を吐露してしまったようだ。
彼としては、なにも偉そうなことをいう性格の人間ではないのだが、いやむしろ反対の性向だが、ただ、毎日を人間らしく生きたいがためにもがいている。
彼が聞いたある人の言葉、
「何が人を人であるとしているかは、一にその人が、毎日を学び続ける、その努力をしている、かどうかということにある。」
を、今思い出している。
完
Posted by 雄一郎 at 2010年06月06日 12:36
>雄一郎様
熱筆、お疲れ様 (^0^;
せめて最後まで読もうと3度チャレンジしましたが。。。。。
3度とも途中で寝てしまいました(汗)
熱筆、お疲れ様 (^0^;
せめて最後まで読もうと3度チャレンジしましたが。。。。。
3度とも途中で寝てしまいました(汗)
Posted by ちょい悪親父 at 2010年06月07日 14:51